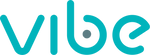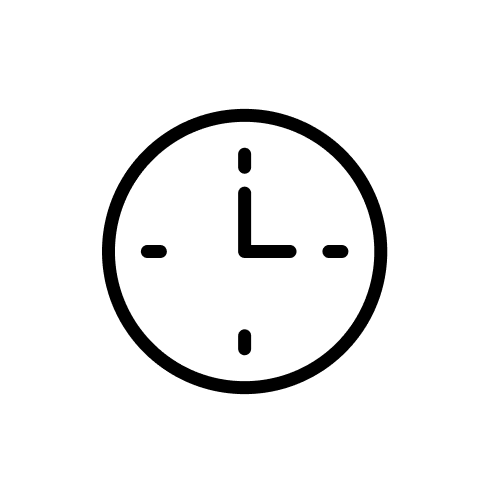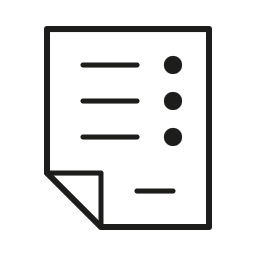デフリンピックって何?東京2025で注目の“静かな”オリンピック【Vibe補聴器ブログ】
1.はじめに:デフリンピックとは?
デフリンピック(Deaflympics)は、聴覚障害者による国際的なスポーツ大会で、スペシャルオリンピック・パラリンピックと並ぶ「世界三大障害者スポーツ大会」のひとつです。
「デフリンピック」という名称は、「Deaf(聴覚障害者)」と「Olympics(オリンピック)」を組み合わせた造語で、2001年から正式に採用されました。
それ以前は「国際ろう者競技大会」や「サイレント・ゲームズ」と呼ばれていました。
この大会の最大の特徴は、聴覚障害者のみが参加する点です。
パラリンピックがさまざまな障害を持つ選手を対象としているのに対し、デフリンピックは聴覚障害に特化しており、手話や視覚的な合図を活用した独自の競技スタイルが展開されます。
また、競技中は補聴器や人工内耳などの聴覚補助機器の使用が禁止されており、すべての選手が「聞こえない」という共通の条件のもとで競い合います。
これにより、競技の公平性が保たれると同時に、聴覚障害者ならではの身体能力や集中力が発揮される場となっています。
デフリンピックは、単なるスポーツ大会ではありません。
聴覚障害者の文化やアイデンティティを尊重し、世界中の人々が手話を通じてつながる「共生の祭典」として、年々その意義が高まっています。
先日、デフリンピックに出場する卓球選手の特集番組を見ました。
競技中は補聴器を外す必要があり、完全な無音の中でプレーするそうです。
卓球ボールを打音がないので、飛んでくるボールのスピードとラケットをうまく合わせることには、頭、体、特に目を使うようです。
練習から、目でボールをしっかり見て、体でリズムを覚えるそうです。
日々の練習では補聴器をつけて聞こえる状態で練習をして、まずは音の力も使って、体にリズムを浸み込ませていくのです。
運動神経に加えて、五感を研ぎ澄まして鍛錬する姿に感銘を受けました。
2.デフリンピックの歴史
デフリンピックの歴史は、1924年にフランス・パリで開催された「国際サイレント競技大会」に始まります。
これは、聴覚障害者による世界初の国際的なスポーツイベントであり、当時9カ国から約145人の選手が参加していたようです。
この大会は、聴覚障害者の社会的認知を高める画期的な試みとして、世界中のろう者コミュニティに大きな影響を与えたのです。
この大会を主催したのは、フランスのろう者活動家・スポーツ指導者であるエウジェン・ルベロンです。
彼は「ろう者にも国際的な舞台が必要だ」と考え、オリンピックに倣った大会を創設しました。
彼の功績は、今日のデフリンピックの礎となっています。
その後、デフリンピックは4年に一度開催されるようになり、参加国・競技種目ともに拡大していきました。
冬季大会は1949年にオーストリアで初めて開催され、以降は夏季・冬季ともに定期的に行われています。
2001年、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)は大会名称を「デフリンピック(Deaflympics)」に正式変更。
これにより、オリンピックやパラリンピックと並ぶ国際的なブランドとしての認知が高まりました。
現在では、100カ国以上が参加する世界的な大会へと成長し、聴覚障害者のスポーツ文化を象徴する存在となっています。
2025年に東京で開催される大会は、ちょうど100周年の記念大会。
歴史の節目として、世界中から注目が集まっています。
3.デフリンピックの特徴と意義
デフリンピックは、他の国際スポーツ大会とは一線を画す、聴覚障害者ならではの文化と価値が息づく大会です。
競技のルールや運営方法にも、聴覚に障害を持つ選手たちが最大限に力を発揮できるよう、独自の工夫が施されています。
聴覚に頼らない競技スタイル
デフリンピックでは、補聴器や人工内耳などの聴覚補助機器の使用が禁止されています。
これは、すべての選手が「聞こえない」という同じ条件で競技することで、公平性を保つためです。
スタートの合図やタイムの通知などは、音ではなく光や視覚的なサインで行われます。
例えば、陸上競技ではスタートの合図にフラッシュライトが使われ、水泳では審判が手で合図を送るなど、視覚を最大限に活用した運営がなされています。
国際手話によるコミュニケーション
大会期間中、選手・スタッフ・観客の多くが手話を使ってコミュニケーションを取ります。
特に「国際手話」は、異なる言語背景を持つ人々が意思疎通するための共通手段として活用され、言葉の壁を越えた交流が生まれます。
この手話文化は、デフリンピックを単なるスポーツ大会ではなく、ろう者コミュニティの祭典として位置づける重要な要素です。
インクルーシブ社会への貢献
デフリンピックは、聴覚障害者の社会的認知を高めるだけでなく、手話やろう文化への理解を広げる機会にもなっています。
大会を通じて、障害のある人もない人も共に生きる「インクルーシブ社会」の実現に向けた意識が高まります。
また、デフリンピックに参加する選手たちは、スポーツを通じて自信や誇りを持ち、社会の中で積極的に活躍するロールモデルとなっています。
※「インクルーシブ」とは、すべての人を排除せずに包み込むという意味を持つ言葉です
4.2025年東京大会の概要
2025年に開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」は、デフリンピック史上初めて日本で開催される記念すべき大会です。
さらに、1924年の第1回大会からちょうど100周年を迎える節目の大会でもあり、世界中の注目が集まっています。
📅開催期間と開催地
- 開催期間:2025年11月15日(土)〜11月26日(水)の12日間
- 開催地:東京都を中心に、静岡県・福島県でも一部競技が実施予定
🏅競技種目と会場
- 実施競技は21種目以上。陸上、サッカー、柔道、バレーボール、卓球、水泳など、多彩な競技が展開されます
- 開閉会式は東京体育館で行われる予定
🌸大会ビジョン
東京2025デフリンピックは、以下の3つのビジョンを掲げています:
- デフスポーツの魅力や価値を伝え、人々や社会とつなぐ
- 世界に、そして未来につながる大会へ
- “誰もが個性を活かし力を発揮できる”共生社会の実現
👂大会の特色
- 国際手話によるコミュニケーションが基本
- 視覚的な情報保障(光によるスタート合図、旗による審判の指示など)
- オリンピックと同様のルールで競技が行われるが、聴覚障害者に配慮した運営が徹底されている
🐣大会マスコットとエンブレム
- 公式マスコットは「ゆりーと」。東京都のスポーツ推進大使としても活躍中
- エンブレムは桜の花弁をモチーフにしたデザインで、「輪」と「手」を象徴し、人々のつながりと未来への希望を表現しています
【参考情報】
5.デフリンピックと社会のつながり
デフリンピックは、単なるスポーツ大会ではありません。
聴覚障害者の文化、言語、アイデンティティを尊重し、社会全体に「共生」の価値を問いかける重要なイベントです。
大会を通じて、さまざまな形で社会とのつながりが生まれています。
手話文化の普及と理解促進
デフリンピックでは、国際手話をはじめとする手話が主要なコミュニケーション手段として使われます。
これにより、手話の存在やその美しさ、表現力の豊かさが広く知られるようになります。
大会期間中は、手話通訳者の活躍や手話を使った応援が注目され、手話学習への関心が高まるきっかけにもなります。
学校や地域でも、手話を学ぶ機会が増えるなど、教育的な波及効果も期待されています。
多様性とインクルージョンの象徴
デフリンピックは、障害の有無にかかわらず、すべての人が尊重される社会の実現を目指す「インクルーシブ社会」の象徴です。
聴覚障害者が自らの力で世界とつながり、競技を通じて自己表現する姿は、多様性の価値を体現しています。
また、企業や自治体が大会を支援することで、バリアフリーや情報保障の取り組みが進み、社会全体のアクセシビリティ向上にもつながっています。
社会参加とロールモデルの創出
デフリンピックに出場する選手たちは、スポーツの枠を超えて、聴覚障害者のロールモデルとして社会に影響を与えています。
彼らの活躍は、若い世代に夢や希望を与え、「障害があっても挑戦できる」というメッセージを力強く発信しています。
また、ボランティアや観客として大会に関わる人々も、聴覚障害者との交流を通じて新たな価値観に触れ、共生社会への理解を深める貴重な体験を得ることができます。
6.おわりに:読者へのメッセージ
2025年、東京で開催されるデフリンピックは、スポーツの祭典であると同時に、聴覚障害者の文化や価値を世界に発信する特別な機会です。
100周年という節目を迎えるこの大会は、過去の歴史を振り返りながら、未来への希望をつなぐ場でもあります。
デフリンピックを知ることは、聴覚障害者の生き方や社会との関わりを理解する第一歩です。
そして、手話や視覚的なコミュニケーションの世界に触れることで、私たち自身の「見る力」「感じる力」も豊かになります。
もしこの記事を読んで、少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ大会を応援してください。
観戦に行くのもよし、SNSで情報をシェアするのもよし、ボランティアとして参加するのも素晴らしい選択です。
デフリンピックは、聴覚障害者だけの大会ではありません。
多様性を認め合い、共に生きる社会を目指す「私たちみんなの祭典」です。
執筆チーム名:Vibe 補聴器 ライターチーム
執筆者名:N.Y

 Go
Go
 Air
Air
 Nano8
Nano8
 Mini8
Mini8
 S8
S8
 交換用電池
交換用電池
 交換用耳せん
交換用耳せん
 乾燥器・その他
乾燥器・その他