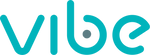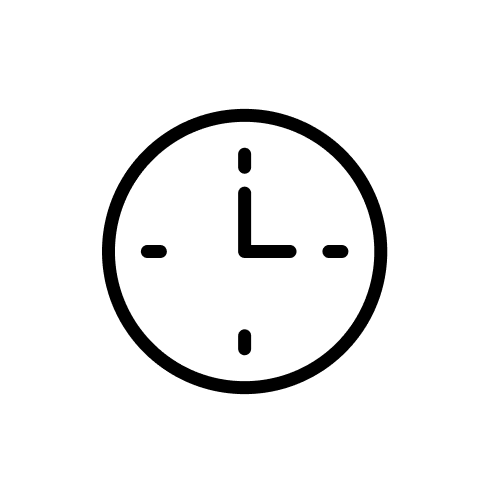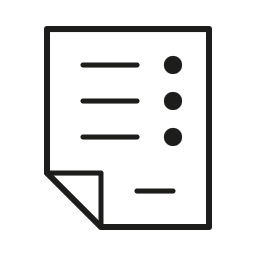『補聴器と健康』:耳の健康を保つためにできること【Vibe補聴器ブログ】
【はじめに】
補聴器は、加齢や環境による「聴こえにくさ」をサポートしてくれる大切なパートナーです。しかし、補聴器だけに頼るのではなく、耳そのものの健康を維持することも、より快適な生活には欠かせません。
本記事では、耳の健康を保つために今日からできる習慣や、補聴器を長く快適に使うためのポイントをわかりやすくご紹介します。
【1. 耳の健康が聴力に与える影響】
〜加齢や生活習慣が“聴こえ”に影響する理由とは?〜
私たちの耳は、年齢とともに少しずつ機能が低下していきます。これは「加齢性難聴」と呼ばれ、特に高い音から聞き取りにくくなるのが特徴です。
また、日常生活の中での大きな音・長時間の騒音環境・ストレス・血行不良なども、聴力に影響を与えることがわかっています。
補聴器は、低下した聴力を補う頼もしいツールですが、その効果を十分に発揮させるには耳自体の健康状態が整っていることが重要です。
【2. 聴力の変化に気づくためのセルフチェック方法】
〜「最近聞こえづらいかも?」と思ったら〜
聴力の低下は徐々に進むため、初期の変化には気づきにくいものです。
以下のような変化を感じたら、注意が必要です。
- 会話中に「え?」「もう一度言って」と聞き返すことが増えた
- テレビやラジオの音量が以前より大きくないと聞き取りづらい
- 電話の声が聞こえにくい
- 集中していないと話が理解しにくいと感じる
自宅で簡単にできる聴力チェックツールやアプリもありますが、「少しおかしいな」と思った段階で専門家に相談するのがベストです。
【3. 日常生活でできる耳の健康管理法】
〜毎日の習慣が“聴こえ”を守る〜
耳の健康は、日々の生活習慣で守ることができます。
以下のようなポイントを意識してみましょう。
音環境の工夫
- 大音量での音楽鑑賞を避ける
- 耳に密着するイヤホンの使用時間を制限する
- 騒音の多い場所では耳栓などを活用する
健康的な生活習慣
- 質の良い睡眠を確保する
- ストレスを溜め込まない(血流や神経に悪影響)
- 喫煙を控える(内耳への血流が悪くなります)
耳掃除の注意点
耳の中はとてもデリケート。奥まで綿棒を入れると、かえって傷つけたり耳垢を押し込んでしまうことがあります。基本的には外側(入口)だけをやさしく拭う程度で十分。耳垢が気になる場合は、耳鼻科での処置をおすすめします。
【4. 補聴器のケアとメンテナンスの重要性】
〜補聴器を快適に使い続けるために〜
補聴器を長く使うためには、正しいお手入れが欠かせません。
毎日のケア
- 使用後はやわらかい布で汗や汚れを拭き取る
- 耳垢がたまりやすい部分(音の出口など)を定期的に清掃
- 湿気対策として乾燥ケースに入れて保管
定期的な点検・調整
聴力の変化や生活スタイルの変化に応じて、補聴器の設定も見直す必要があります。少なくとも半年〜1年に1回は専門店での点検・再調整をおすすめします。
電池や充電の注意点
- 電池式の場合は予備を常備しておく
- 充電式の場合は毎晩忘れずに充電
- 電池の液漏れや膨張がないかも定期的にチェック
【5. 栄養と耳の健康】
〜食事から“聴こえ”を守る〜
耳の健康にも、食生活は大きく関わっています。特に次の栄養素は、聴力維持に役立つとされています。
- ビタミンB群(神経の働きを助ける)
- 亜鉛(内耳の代謝をサポート)
- マグネシウム(血流を改善)
- ビタミンC・E(抗酸化作用で細胞を守る)
栄養バランスのとれた食事を心がけることで、耳の機能を支える体のコンディションも整えることができます。
【6. 専門家への相談と定期検査のすすめ】
〜自己判断せず、専門の方に相談を〜
聴力の変化を感じたとき、自己判断で済ませてしまうと、対処が遅れたり、状態が悪化してしまうこともあります。
早めの相談がカギ
- 「聞こえづらい」と感じたら耳鼻科へ
- 補聴器を使用している場合も、年に1回程度の聴力検査がおすすめ
補聴器専門店でのアフターケアも活用
- 機器の点検・メンテナンス
- 聴力の変化に合わせた再フィッティング
- 新しい機能や製品の相談
【まとめ】
補聴器は聴こえをサポートする頼もしい味方ですが、それを支える「耳の健康」こそが、快適な毎日の鍵となります。
日々のちょっとした工夫やケアを積み重ねることで、補聴器の効果を最大限に活かし、生活の質をより高めることができます。
執筆チーム名:Vibe 補聴器 ライターチーム
執筆者名:N.Y

 Go
Go
 Air
Air
 Nano8
Nano8
 Mini8
Mini8
 S8
S8
 交換用電池
交換用電池
 交換用耳せん
交換用耳せん
 乾燥器・その他
乾燥器・その他